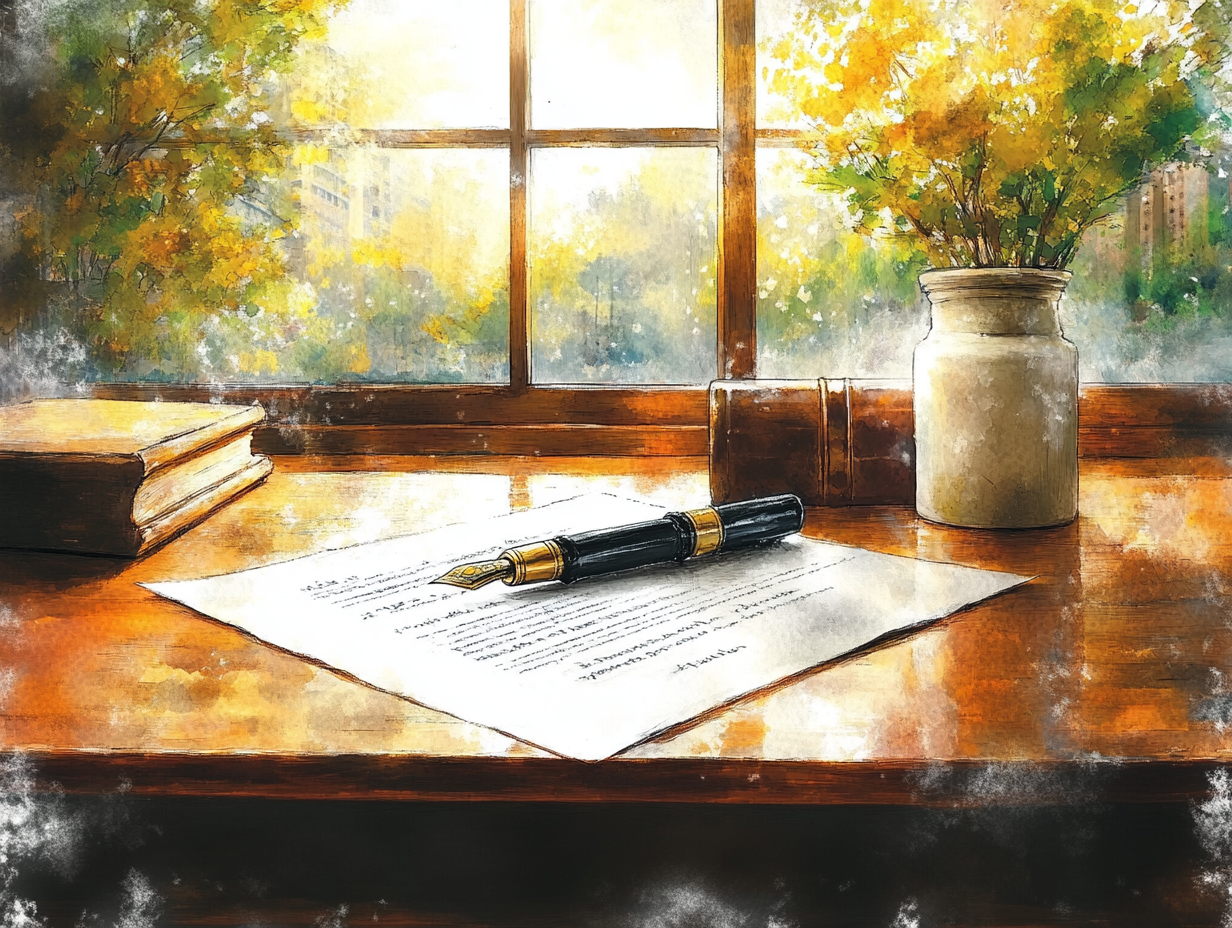名もなき介護とは
介護と育児のダブルケアのSakuです。
介護において、記録には残らない細々とした作業や心配りのことを「名もなき介護」と呼びます。
これは介護する側の大きな負担となりますが、あまり注目されていません。
私は両親の急な入院とショートステイを経験し、その持ち物準備で「これが名もなき介護」ではと思ったので
共有したいなと思います。
初めての持ち物の準備で混乱
急な入院やショートステイが決まり、さらにはそれがどれも初めてだと何をどれだけ持ち込むべきか分からず、想像以上に混乱しました。
しかも、今回は、父は急遽入院となり本人不在での準備、父が入院した次の日に母も契約当日にショートステイ先に行くため、とりあえず必要なものを詰め込むといった状況でした。
本人が普段は使い慣れている入れ歯入れやメガネですら、本人以外は把握していないので探すだけで一苦労でした。
とりあえず持ち込み終わっても続きがある!?
とりあえず準備して、これで終わりかと思ったら、その後も持ち込みは続きました。。。
持ち物リストにそって準備したけど、実際はこれが必要だから持ってきてほしいと追加なものが出てきました。
父は病院、母はショートステイ先にいて家には2人とも不在でした。
だからどちらかに家で直接聞ける状況でもなく、家で見つからないときはそれぞれの必要物品を揃えるため、あちこち走り回り、買うことになりました。
困ったのは消耗品や日常品管理です。例えば:
- ティッシュ、マスクの残量確認。最初の持ち込みで1箱ずつで良いかと思ったのですが、後ほど、無くなって追加補充が多々ありました。
日常品の把握の難しさ
「普段使いの物は何か」という単純な質問でさえ、意外と答えるのが難しいものです。
タンスの中には毛玉だらけの古い服やら新品同様の服やらが混在しており、そこから本人お気に入りの着慣れた服なのか、判断できませんでした。
とりあえず着れそうな服を準備して持っていきました。
しかし、後ほど、「この服が欲しい」「この羽織が欲しい」と追加依頼が。
とにかく持ち物の追加が続くのでした。
混乱と手間を防ぐための事前準備のポイント

この経験から、普段からの準備と整理の重要性を感じました。
特に追加の持ち込みが手間でした。どこにあるか探す手間。なければどこかに購入したり、探したりする手間。
以下のポイントを意識することで、緊急時の混乱や自身の手間を省けるかと思います。
- 必需品の見える化
- 日用品の保管場所を家族で共有
- 使用頻度の高い物は取りやすい場所に配置
- 必需品リストの作成と定期的な更新
- 衣類の整理
- 着慣れた服を明確に区別
- 季節ごとの衣類の整理
- サイズや好みの特徴をメモ
- 消耗品の管理
- 使用量の把握と予備の確保
- 定期的な在庫チェック
- 補充のタイミングを決める
事前準備がもたらす安心感
今回の両親の急な入院やショートステイは想定外でした。
日頃から使用している物の場所と量を把握し、必要に応じてメモを残すことで、緊急時の対応もスムーズになります。
また、「もしも」の時に慌てないよう、少しずつでも準備を始めることをお勧めします。
予期せぬ事態が起きても、事前の準備があれば、より落ち着いて対応できるはずです。
突然の出来事に備え、できることから少しずつ準備を始めてみませんか。