介護と育児をしているSakuです。
子育ても、介護も、──全部を自分で背負い続けて、もう限界…そう感じていませんか?
子育ては母である私がやるしかない!親の介護は子供である私がやるしかない!と思い込んで突き進んでいないでしょうか?

Saku
私は、介護も育児もそして、仕事もしているのでその状況の中で一人で抱え込むのは無理な状態でした。
そんな私が、思っているダブルケアの現状や対応策等を紹介していきます。
| この記事を読んで分かること |
|---|
| 子育ても介護も、全部がんばっているあなたへ。この記事では、ダブルケアの現状や限界を感じたときに無理せず続けていくための具体的な対策をお伝えします。 |
1. ダブルケアとは?今、増えている“二重の負担”の実態3つ
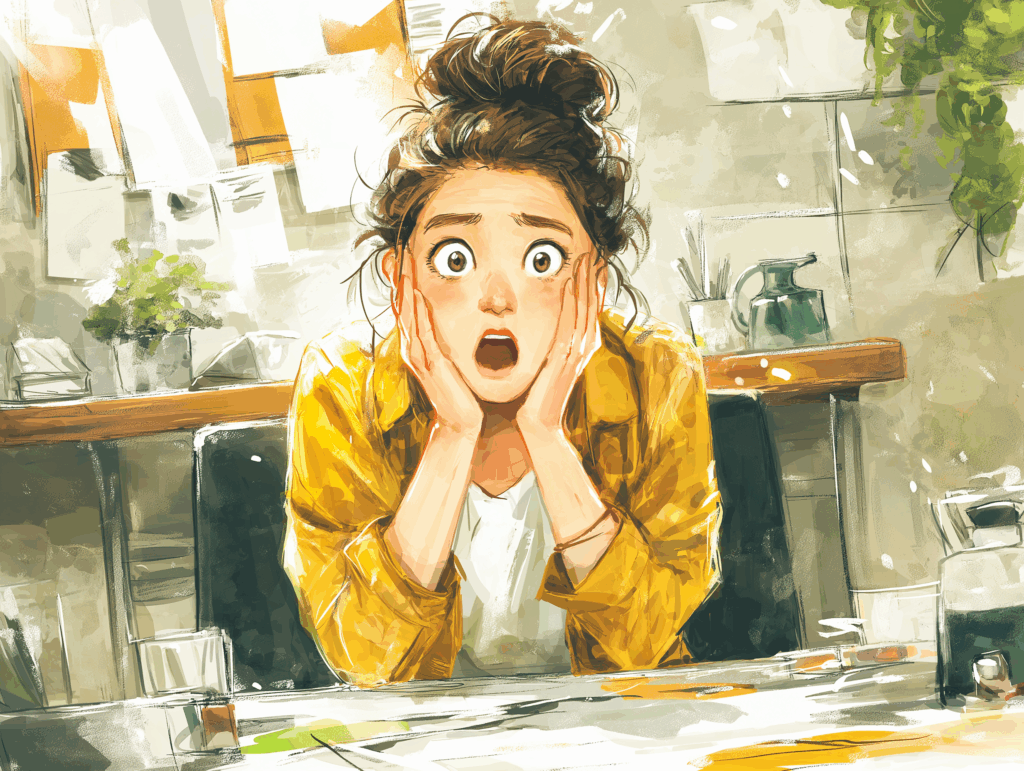
子育ても介護も、どちらか一方でも大変なのに、その両方を同時に担わなければならない人が、いま増えています。 これが「ダブルケア」と呼ばれる状況です。
ここでは、実際に多くの人が直面している“ダブルケアの3つの実態”について解説します。
①晩産化と長寿化が重なり、ダブルケア層が急増
晩産化と長寿化により、子育てと介護の時期が重なる家庭が増えています。
出産年齢が上がっている一方で、親世代が長生きするため、子どもがまだ幼い時期に親の介護が始まるケースが多くなっています。
厚生労働省の統計によると、第一子出産の平均年齢は30歳前後、親が介護を必要とするのはおおむね75歳以降が中心です。

Saku
実際、私の親も75歳前後で介護が開始となりました。
②共働き家庭が多数派で、時間的余裕がない
共働きが当たり前になったことで、家庭内でダブルケアの負担を分散できなくなっています。
共働きでどちらも働いているうえに、子育てと介護の時間が勤務時間と競合し、時間確保するのが難しい状況です。
総務省の調査では、子どもがいる共働き世帯の割合は70%を超えています。
③相談できる人がいない“孤独なケア”が増加
家族や親戚に頼れず、すべて自分ひとりで対応せざるを得ない人が増えています。
地域や親戚との関係が希薄になり、また兄弟姉妹がいない・遠方に住んでいるなどの理由から、相談・分担できる相手がいない状況に陥りやすくなっています。

Saku
一人っ子である私も特に介護についてはなかなか周りに相談するには躊躇してました。介護となると何か重い感じになるのではと思う部分もありました。
2. 投げ出したくなるのは、心と体が限界という“サイン”5つ

「もう無理」「全部投げ出したい」と感じると、自分を責めてしまう人が多いかもしれません。でもその感情は、心や体が出している重要なサイン。無理を続ければ、いずれ共倒れになってしまうかもしれません。
ここでは、ダブルケアに直面している人が見逃しがちなサインを5つ紹介します。
①いつもイライラして、家族にきつく当たってしまう
感情のコントロールが難しくなるのは、ストレスが限界に近い証拠です。

Saku
心に余裕がなくなると、些細なことで怒りが爆発し、後で自己嫌悪に陥る悪循環が起きます。余裕を持つのは難しいですが、自分の気持ちも整理しながら付き合っていきましょう。
②些細なことで涙が出る、笑えなくなった
感情の振れ幅が極端になったときは、心のエネルギーが枯渇しているサインです。
無理に明るく振る舞うことに疲れ、ちょっとした刺激に過剰に反応する状態になっています。
心理カウンセリングの現場では「笑えない・泣きやすい」はうつ症状の初期兆候として扱われています。
③夜ぐっすり眠れない、朝起きるのがつらい
睡眠に不調を感じたら、心身がSOSを出していると受け止めてください。
ストレスは自律神経の働きを乱し、眠りが浅くなったり、寝ても疲れが取れない状態を引き起こします。
④人と話すのが面倒くさい
コミュニケーションを避けたくなるのは、心が「これ以上刺激を受けたくない」と感じているからです。
会話ややり取りで気を使うことすら負担になり、孤立へと向かうリスクが高まります。
⑤やることが多すぎて、何も手につかなくなる
タスクの優先順位がつけられなくなったときは、脳が過負荷状態にある可能性が高いです。
頭の中がいっぱいになり、どれから手をつけていいかわからず、結果的に何も進まない状態に陥ります。

Saku
実際、私も育児も介護もやることがどんどん増えると「もう、何もやりたくない!」と投げ出したい気持ちが沸き上がることはよくあります。
3. 実際にどうやって乗り越える?ダブルケアの具体的な対策4選

投げ出したくなるほどの毎日。それでもダブルケアは“なくなる”わけではありません。だからこそ、ひとりで抱え込まず、少しずつ負担を減らす工夫が必要です。
今日から取り入れられる”具体的な対策を4つ”ご紹介します。
①地域包括支援センターを頼る
まず最初に相談するべきは、お住まいの地域包括支援センターです。
介護の支援制度を横断的に把握しており、必要なサービスを整理して提案してくれます。

Saku
何も分からなかった介護。地域包括センターを頼ることで道が少しづつ見えてきました。
②育児・介護の“プロ”に思い切って任せる
デイサービスや一時保育など、専門の支援サービスを使うことで自分の時間を確保できます。
身内の手助けが得られないときこそ、公的・民間の支援に頼ることが現実的な選択肢です。
③タスクを「やる・やらない」で明確に分ける
すべてを完璧にこなそうとせず、優先順位を決めて“やらないこと”を意識的に選びましょう。
限られた時間と体力の中で、必要なことだけに集中することで、ストレスとミスを減らせます。
④「自分を最優先にする日」をあえて作る
週に一度でも「何もしない日」「好きなことだけする時間」を確保することで、回復力が大きく変わります。
自分をケアしないまま他人に尽くし続けると、心も体も壊れてしまいます。

Saku
なかなかこの時間を確保するのは難しいです。ただ、5分でも10分でも自分の時間を確保出来るようにして自分を大切にして欲しいです。
よくある質問とその回答
- ダブルケアは一時的なものだと思ってもいいのでしょうか?
状況によっては一時的に集中してケアが必要になる時期もありますが、終わりが見えにくいのが現実です。だからこそ「長期戦を見据えた工夫」が必要であり、短期的に無理をすると後で大きな負担になります。
- 頼れる人がいない場合、本当に公的サービスだけで乗り切れるのでしょうか?
公的サービスだけで完璧に回るとは言い切れませんが、頼れる土台にはなります。その上で、民間サービスやオンライン支援なども上手に組み合わせることで、現実的な対応が可能になります。
- ダブルケアが始まる前に備えておくべきことはありますか?
はい、情報収集と家族内での役割確認が特に重要です。介護や育児の公的支援、緊急連絡体制などを事前に整理しておくと、いざというとき落ち着いて動けます。
- 介護・育児・仕事のどれも中途半端になっている気がしてつらいです。
すべてを100点でこなそうとするのは不可能です。時には優先順位を見直しながら「今の私にできること」で十分だと自分に許可を出すことが、継続のカギになります。
- 周囲に比べて自分だけ大変だと感じてしまいます。
その感情は自然なものです。他人の状況は見えにくいため、自分が最も苦しんでいるように感じがちです。だからこそ比較をやめて、「自分が今どう感じているか」に正直になることが大切です。
まとめ
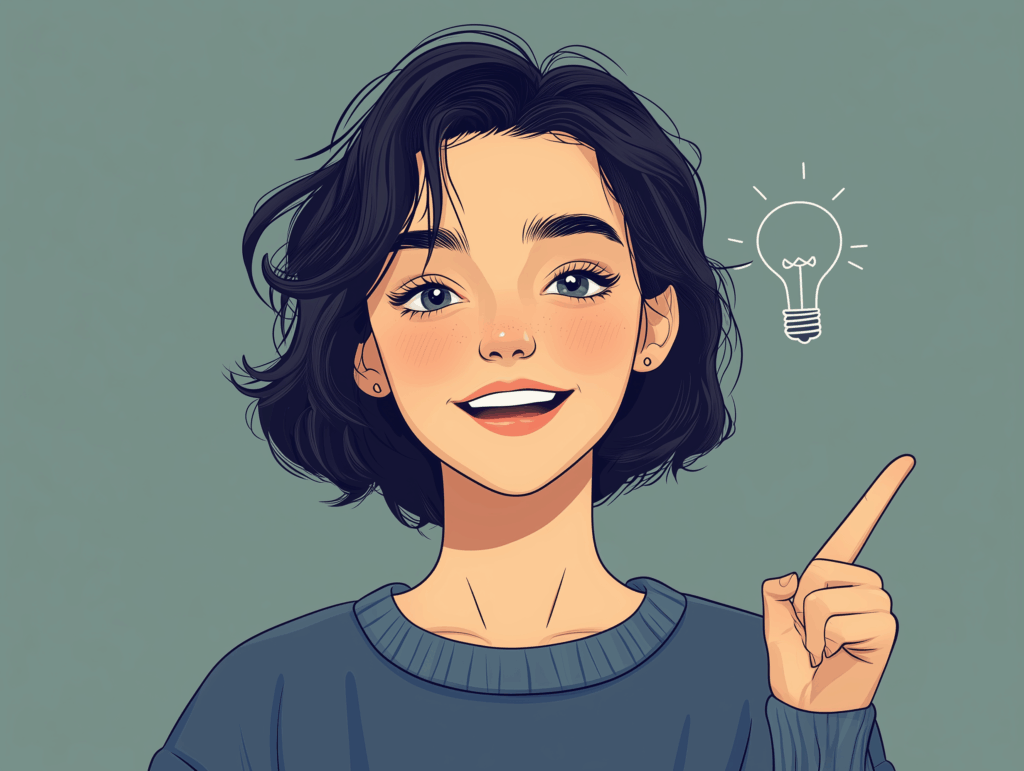
この記事のポイントをまとめました。
- ダブルケアは晩産化と長寿化が重なって生じる現代的課題で、育児と介護の二重負担を抱える人が増えています。
- 「もう無理」と感じるのは甘えではなく、心と体が限界に達した重要なサインとして受け止めることが大切です。
- 地域の支援機関や外部サービスを上手に活用し、自分だけで抱え込まない仕組みを作ることが乗り越えの第一歩です。
- 家族や他者に頼ることは責任放棄ではなく、自分を守りながらケアを継続するために必要な選択肢です。
- 限界を感じたときこそ、自分の暮らしや考え方を見直すチャンスであり、立ち止まることは前進への準備です。
育児と介護のダブルケアをしいると想定外のことばかりが多数発生します。それを自分だけで抱え込まないで頼ることは必要だと思います。

Saku
色んなことを対応するにも、自分の体調や精神面を大切することが重要です。どうかご自愛くださいませ。


