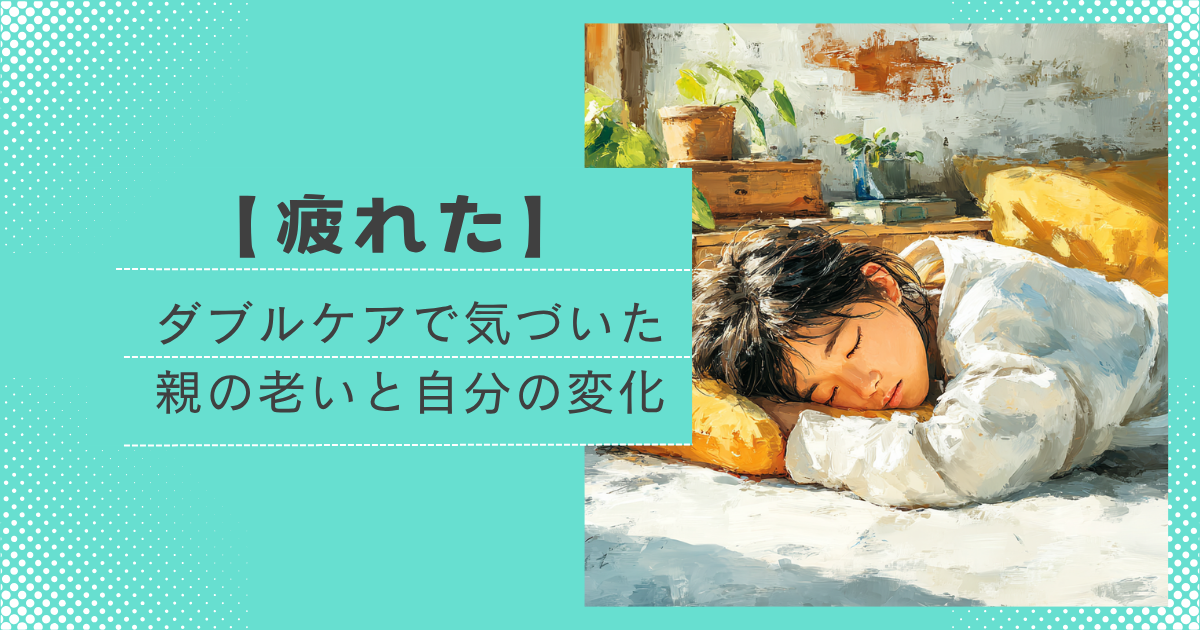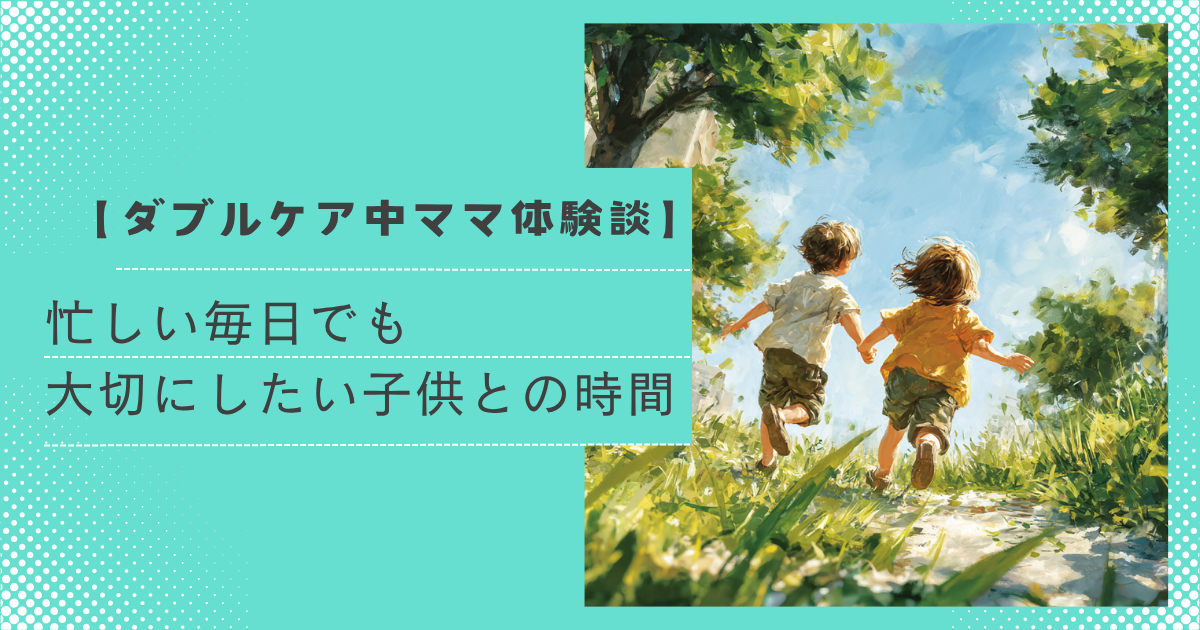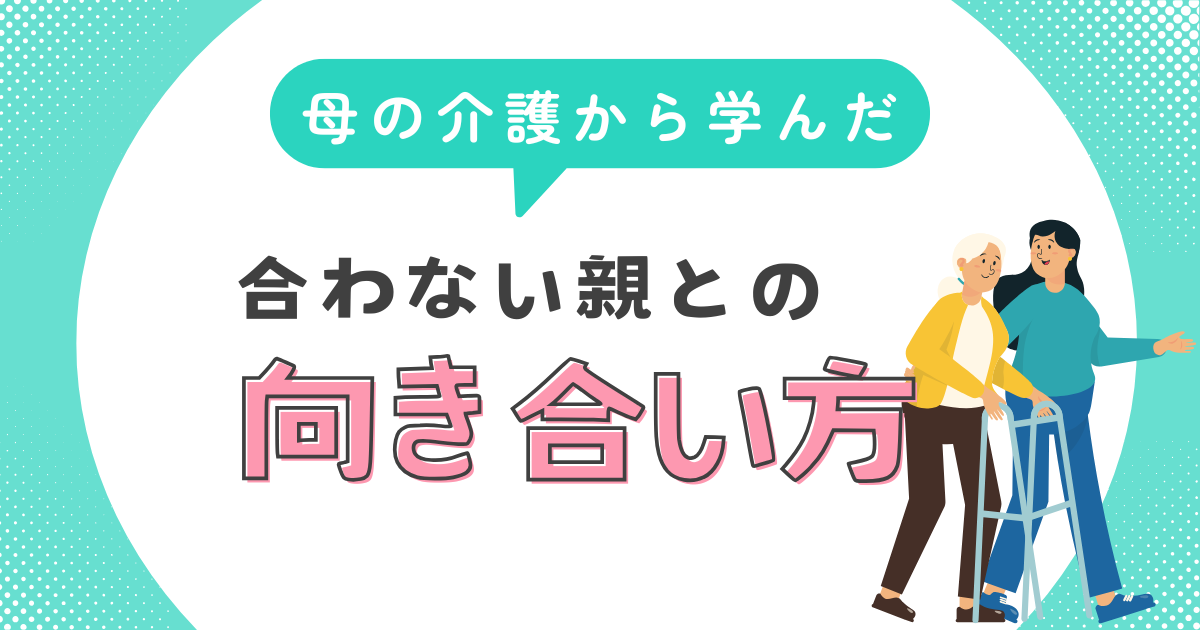育児と介護のダブルケアをしているSakuです。
最近、父の歩行が不安定になり杖なしでは外出が困難になってきました。
一方で、子供たちは元気いっぱいで私の体力を容赦なく奪っていきます。
そんな日常の中で、「老い」について深く考えさせられることがありました。
今回は、親の変化を目の当たりにして感じた率直な思いをお話しします。
親の身体機能低下を受け入れることの難しさ

Saku
親の老いを受け入れるのは想像以上に辛いものです。それは元気な親の姿を知っていてどうしてもそのときと比較してしまうことがあるからです。
なぜ受け入れが困難なのか
父は今、杖がないと歩くのが危うい状況になっています。
ちょっとそこまで散歩に出かけたり、バスや電車を利用するためにバス停や駅まで歩いたりするのが困難になってきました。
年齢を重ねれば体の自由が利かなくなり、今までできたことができなくなる。
頭では分かっていても、実際に目の当たりにすると「まだ早いんじゃないか」「もう少し頑張れるのでは」と思ってしまうんですよね。
段階的な変化だから余計に複雑
それは段々とそのようになるから受け入れられるものなのでしょうか。私自身、この疑問にずっと悩んでいます。
昨日までできていたことが今日はできない、というわけではなく、少しずつ、本当に少しずつ変化していく。
だからこそ、「まだ大丈夫」と思いたい気持ちと、「現実を受け入れなければ」という気持ちの間で揺れ動いてしまいます。
自分自身の体力低下との向き合い方

ただ、そんな私自身も、子供たちとの日常で体力の限界を感じる瞬間があります。
育児中の体力低下は避けられない現実
私自身は、腰が痛いなとか肩がこるなということはあっても、まだ生活に支障をきたすほどではありません。
でも、パワフル全開の子供たちと接していると、時々疲れてしまい「休憩したい」と思って、近くのベンチに座っちゃうことがあります。
子供の反応から気づいた大切なこと
そんな時、子供たちは「母ちゃん休憩しないで!」と言ってくるんです。
子供からすれば、なんでこんなことで休んでいるのって感じなんですよね。
この反応を見ていて、ふと思ったことがあります。
もしかして、年齢を重ねるごとに段々とできないことを自ら選んでいるのかもしれません。
「疲れたから休む」「面倒だからやめる」そういう小さな選択の積み重ねが、全くできない状態につながっているのかもしれないんです。
「やる気次第」で老いのスピードは変えられる

そう考えると、できていたことをいつまでもできるようにし続けるには「本人のやる気次第」なのかもしれません。
体力・気力の低下は避けられないが、スピードは調整可能
体力も気力も年齢を重ねれば失われていくかもしれませんが、その低下スピードを遅らせるのは結局本人次第だと思います。
完全に止めることはできないけれど、「今日はちょっと頑張ってみよう」「まだできるかも」という気持ちを持ち続けることで、現状維持や緩やかな低下に留めることは可能なのではないでしょうか。
ダブルケアだからこそ見えてくる視点
ダブルケアをしている立場だからこそ、親の変化と自分の変化を同時に観察できています。
そして分かったのは、年齢に関係なく「やってみよう」という気持ちの大切さです。
私も子供たちに「母ちゃん休憩しないで!」と言われた時、「確かに、もう少し頑張れるかも」と思い直すことがあります。そういう小さな意識の変化が、きっと大きな違いを生むのだと思います。

Saku
こうやって意識変化をしていこうと思うのですが、ときよりエンジンかからずのときもあるのでマイペースでやっていこうと思っています。
まとめ
- 親の老いを受け入れることは想像以上に辛く、段階的な変化だからこそ「まだ大丈夫」と思いたい気持ちと現実の間で揺れ動くのは自然な感情です。
- 年齢を重ねるごとにできないことを自ら選んでいる可能性があり、意識的に「やってみよう」という気持ちを持つことが大切だと実感しています。
- ダブルケアの立場だからこそ親の変化と自分の変化を同時に観察でき、年齢に関係なく「やってみよう」という気持ちの大切さを学びました。

Saku
ダブルケアをしている皆さん、親の変化に戸惑うことがあっても、それは自然な感情です。
でも、その経験を通して気づいたことを、ぜひ自分自身の生活にも活かしてみてください。小さな「やってみよう」の積み重ねが、きっと未来の自分を支えてくれるはずです。